
この人を見よ ヨハネによる福音書19章1~16a節 2025年4月6日
聖書―ヨハネによる福音書19章1~16a節
(はじめに)
いよいよ来週から、受難週です。受付のところに、受難週の出来事が書かれている聖書個所の表と、イースターの説明が書かれた印刷物がありますので、お持ち帰りくださって、そこに書かれている聖書個所を読みながら、受難週の時を過ごしていただければさいわいです。
教会学校では、『聖書教育』の聖書個所から学んでいますが、マタイによる福音書の言葉から、イエスさまの十字架、そして、復活を学んでいくことになります。礼拝では、ヨハネによる福音書の言葉から、イエスさまの十字架と復活を学んでいきたいと思います。
(聖書から)
お読みしたヨハネによる福音書19章1節からです。
19:1 そこで、ピラトはイエスを捕らえ、鞭で打たせた。19:2 兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭に載せ、紫の服をまとわせ、19:3 そばにやって来ては、「ユダヤ人の王、万歳」と言って、平手で打った。
今朝の教会学校では、マタイによる福音書26章47~56節から学びました。イエスさまがいよいよ捕らえられて、大祭司のもとに連れて行かれるという個所でした。礼拝でお読みした個所では、大祭司のもとに連れて行かれた後の内容になります。
イエスさまは、ユダヤの大祭司に尋問された後、ローマからユダヤの総督として立てられていたピラトのもとに連れて行かれました。このピラトから、イエスさまは尋問されましたが、イエスさまには何の罪も見当たらない(18章38節)、という結論でした。しかし、ユダヤ人たちは、イエスさまをローマの刑罰である十字架につけてほしい、と願ったのです。これはローマの刑罰の中でも極刑で死刑のことです。当時、ユダヤはローマの支配下にありました。イエスさまを亡き者にしようと考えたユダヤのある人たちが、イエスさまをローマの反逆者であるとして政治犯に仕立ててローマの刑罰を受けさせようとしたのです。
1節には、「ピラトはイエスを捕らえ、鞭で打たせた」とあります。ピラトは、イエスさまには何の罪も見当たらないから、十字架刑にする必要はない、と判断しましたが、ユダヤ人たちを納得させるために、鞭打ちの刑で収めようとしました。一方、ローマの兵士たちが、イエスさまをからかい、侮辱した様子も書かれていました。彼らは、イエスさまの頭に茨の冠をかぶせ、紫の服を着せました。冠というのは、ご存じのように王さまが頭にかぶるものでした。しかし、それが茨で編んだものでしたから、頭にそのとげが刺さり、血が流れたことでしょう。紫の服というのは、皇帝など、高貴な人の着る衣装でした。茨の冠をかぶせ、紫の服を着せ、その顔を平手で打ち、「ユダヤ人の王、万歳」と言って、イエスさまをからかったのです。
ピラトは、イエスさまをどうにかして、無罪放免にしたかったようです。そこで次のようなことをしました。
19:4 ピラトはまた出て来て、言った。「見よ、あの男をあなたたちのところへ引き出そう。そうすれば、わたしが彼に何の罪も見いだせないわけが分かるだろう。」19:5 イエスは茨の冠をかぶり、紫の服を着けて出て来られた。ピラトは、「見よ、この男だ」と言った。
ここでも、ピラトは、こう言っています。「彼に何の罪も見いだせない」。茨の冠をかぶせられたまま、紫の服を着せられたままの格好で、イエスさまは、みんなの前に出てきました。この時、ピラトは、こう言っています。「見よ、この男だ」。これは、「見よ、この人だ」(口語訳、聖書協会共同訳)とも訳されます。私は、「見よ、この男だ」、「見よ、この人だ」という言葉を聞くと、新生讃美歌の205番、教団讃美歌では121番の賛美歌を思い出します。「まぶねの中に」という賛美歌です。四節までありますが、その歌詞をお読みします。
1 馬槽(まぶね)の中に うぶごえあげ 木工(たくみ)の家に 人となりて
貧しきうれい 生くるなやみ つぶさになめし この人を見よ
2 食するひまも うちわすれて しいたげられし 人をたずね
友なきものの 友となりて 心くだきし この人を見よ
3 すべてのものを 与えしすえ 死のほかなにも むくいられで
十字架のうえに あげられつつ 敵をゆるしし この人を見よ
4 この人を見よ この人にぞ こよなき愛は あらわれたる
この人を見よ この人こそ 人となりたる 活ける神なれ
この賛美歌の中に繰り返し出てくる言葉が、「この人を見よ」です。ピラトという人は、ユダヤ人ではなく、神さまを信じる人でもありませんでした。そのピラトが、イエスさまを尋問する中で、イエスさまには、罪がない、ということを、イエスさまを訴えたユダヤ人たちに知らしめるために、こう言っているのです。
6節以下をお読みします。
19:6 祭司長たちや下役たちは、イエスを見ると、「十字架につけろ。十字架につけろ」と叫んだ。ピラトは言った。「あなたたちが引き取って、十字架につけるがよい。わたしはこの男に罪を見いだせない。」19:7 ユダヤ人たちは答えた。「わたしたちには律法があります。律法によれば、この男は死罪に当たります。神の子と自称したからです。」
ピラトは、イエスさまには何の罪も見いだせない、と言いましたが、祭司長たちや下役たちは、「十字架につけろ。十字架につけろ」と叫びました。なぜ、彼らは、このようなことを言ったのかというと、イエスさまが、「神の子」と自称したからだ、というのです。イエスさまを「神の子」と認めない、信じない彼らにとっては、それは律法に違反すること、神さまを冒涜することであり、死に当たることだ、というのです。
これを聞いたピラトはどうしたかというと、8節以下にこのように書かれています。
19:8 ピラトは、この言葉を聞いてますます恐れ、19:9 再び総督官邸の中に入って、「お前はどこから来たのか」とイエスに言った。しかし、イエスは答えようとされなかった。19:10 そこで、ピラトは言った。「わたしに答えないのか。お前を釈放する権限も、十字架につける権限も、このわたしにあることを知らないのか。」19:11 イエスは答えられた。「神から与えられていなければ、わたしに対して何の権限もないはずだ。だから、わたしをあなたに引き渡した者の罪はもっと重い。」
ピラトは恐れた、それも、ますます恐れた、というのです。ピラトは、イエスさまには何の罪もないことは分かっていました。だから、総督としての権限で釈放することができたはずです。しかし、ピラトは恐れたのです。何を恐れたのでしょうか。人を恐れたのです。
人を恐れる。それは、ある意味では大事なことです。人の善意や良心、また人の命の尊厳、そのことに対して恐れるということは大事です。その恐れがなくなると、人を人とも思わなくなるのです。人を人とも思わない、恐れのない指導者、国というものがあることを私たちは知っています。しかし、ピラトの恐れというのは、それとは違います。ピラトは、人の悪意や罪の心を恐れたのです。恐れをなしたピラトは、イエスさまに直接、尋ねています。「お前はどこから来たのか」。あなたはどこから来たのか?という問いです。ピラトは、イエスさまには罪がないことは分かっていましたが、イエスさまがどこから来たのか、そのことは分かっていませんでした。
イエスさまは、この問いには何も答えませんでした。すると、ピラトは、イエスさまにこう言いました。「わたしに答えないのか。お前を釈放する権限も、十字架につける権限も、このわたしにあることを知らないのか」。ここで、ピラトは、権限の話をしています。自分には、権限がある。イエスさまを釈放する権限がある。また、イエスさまを十字架につける権限もある、というのです。
それに対して、イエスさまは、このように言われました。「神から与えられていなければ、わたしに対して何の権限もないはずだ。だから、わたしをあなたに引き渡した者の罪はもっと重い」。ピラトは、自分には、釈放する権限も、十字架につける権限もあると言いましたが、イエスさまは、その権限は誰から与えられたのか、その権限はどこから来たのか、ということを言われたのです。「神から与えられていなければ・・・」とありますように、その権限は神さまから与えられたのだ、その権限は神さまから来たのだ、とイエスさまは言われたのです。すると、このイエスさまの言葉から、ピラトがイエスさまに尋ねた「お前はどこから来たのか」、このことも分かるはずです。イエスさまはどこから来られたのか。神さまから来られた方、神さまのみ子、それがイエスさまです。
(むすび)
ピラトは、イエスさまとのこの対話によって、イエスさまが神さまから来られた方。神さまのみ子であるということを認め、信じたのでしょうか?いいえ、そうではありませんでした。ですから、この後、ユダヤ人たちの強い要求に押されてしまい、恐れをなし(12、15節)、ついには、イエスさまを十字架につけることになったのです(16節)。
この人を見よ。ピラトは、イエスさまには罪がないことを知り、「見よ、この男だ」と言いました。しかし、ピラト自身は、イエスさまを神さまから来られた方、神さまのみ子と信じることはありませんでした。ピラトは、ユダヤ人たちに、イエスさまのことをこう言っています。「見よ、あなたたちの王だ」(14節)。ピラトは、「見よ、私の王だ」とも、「見よ、私たちの王だ」とも、言うことができませんでした。
先ほどの賛美歌の三節の歌詞をもう一度、お読みします。
すべてのものを 与えしすえ 死のほかなにも むくいられで
十字架のうえに あげられつつ 敵をゆるしし この人を見よ
まさにこの歌詞が示すような出来事が起こりました。この歌詞には、イエスさまの十字架の意味が歌われています。イエスさまは十字架につけられました。私たちを赦すために、私たちを罪から救うために、イエスさまは十字架につけられました。教会暦、教会のこよみを重んじる教会では、3月5日から、レント、四旬節として、イースター、復活祭までの四十日間、イエスさまの十字架と復活を思いつつ、断食をしたり、節制をしたり、祈りに専念したりして、日々を過ごします。私たちも、私たちのために主がなさった救いのみわざ、十字架と復活をおぼえながら、一日一日を過ごしてまいりたいと思います。
祈り
恵み深い私たちの主なる神さま
総督ピラトは、イエスさまが罪のないお方であることは知っていました。それで、この人を見よ、と言いましたが、この人は私の主、私たちの主と言うことはできませんでした。しかし、今、私たちは、人々に、この人を見てください。この人こそ、私の主、私たちの主です、と告白することができるように、あなたが導いてくださったことを感謝します。そして、どうか、私たちをこれからも、十字架のみわざを伝える者として用いてくださいますようにお願いします。
私たちの救い主イエス・キリストのみ名によってお祈りします。 アーメン




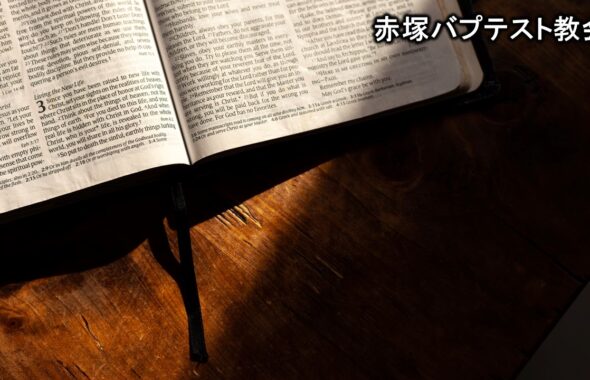



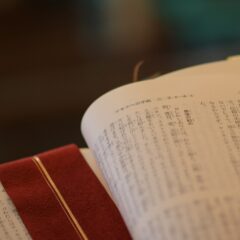

この記事へのコメントはありません。