
神の子の自由 マタイによる福音書17章22~27節 2025年5月11日
聖書―マタイによる福音書17章22~27節
(はじめに)
「からし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かって、『ここから、あそこに移れ』と命じても、そのとおりになる。あなたがたにできないことは何もない」(17章20節)。これは、先週お読みした聖書の言葉です。イエスさまは、病を癒すことができなかった弟子たちに、からし種一粒ほどの信仰があればよい、と言われました。このイエスさまの言葉から知らされることは、弟子たちには、からし種一粒ほどの信仰もなかった、ということです。そういう弟子たちに対して、イエスさまは、大きな信仰を持つようになりなさい、強い信仰を持つようになりなさい、とは言われませんでした。からし種一粒ほどの信仰があれば、それでよい、と言われたのです。
ところで、この話の中で、イエスさまは、「からし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かって、『ここから、あそこに移れ』と命じても、そのとおりになる」とも言われました。山を移す信仰です。山を移すなんて、イエスさまは、何と不思議なことを言われるのか?と思われる方があるでしょう。これは、文字通りの意味ではありません。当時、ユダヤ人は、不可能と思えることを可能とする。そのことを「山を移す」と表現したのです。私たちには到底できない。どう考えても無理だと思えること。しかし、神さまに信頼していく時、神さまが私たちの思いを超えたみわざを行ってくださる。だから、あなたがたは、祈り続けましょう、求め続けましょう。イエスさまは、そう言われたのです。
実は、この後には、21節の言葉があります。「しかし、この種のものは、祈りと断食によらなければ出て行かない」。これは新共同訳聖書の聖書本文には入っていません。口語訳聖書では、括弧付きの言葉になっています。この21節の言葉は、聖書学の研究によって、後になって付け加えられたものだということが分かって、本文に入れられなかったのです。しかし、ここも併せて読んでみますと、祈りと断食というのは、神さまを信頼して、神さまに委ねていくことですから、決して間違ったことが言われているわけではないと思います。神さまに対する深い信頼をもって歩むことを教えていると思います。
(聖書から)
さて、今日の聖書個所は、22節からです。22、23節をお読みします。
17:22 一行がガリラヤに集まったとき、イエスは言われた。「人の子は人々の手に引き渡されようとしている。17:23 そして殺されるが、三日目に復活する。」弟子たちは非常に悲しんだ。
イエスさまが、ご自分の弟子たちに言われたこと、それは、ご自分が殺されること、そして、三日目に復活することでした。この聖書個所について、新共同訳聖書では、「再び自分の死と復活を予告する」という小見出しが付けられています。「再び」とあるように、イエスさまは、以前にも、弟子たちに、ご自分の死と復活について語られていました(16章21節)。その時には、弟子の一人であるペトロが、「そんなことがあってはなりません」(16章22節)とイエスさまをいさめ始めた、イエスさまを叱ったのです。なぜ、叱ったのかというと、イエスさまが殺されるようなことがあるはずがない、あってはならない、というペトロの思いが、そうさせたのでしょう。このやり取りの直前には、ペトロは、イエスさまのことを「あなたはメシア、生ける神の子です」(16章16節)とイエスさまがメシア、救い主であると告白しているのです。しかし、ペトロの考えていた救い主というのは、イエスさまが言われた救い主とは違っていました。ペトロは、当時のユダヤの人たちの間で考えられていた政治的な解放をもたらす救い主を思い描いていたのです。
そして、今日の個所では、イエスさまは、ご自分の死と復活について、二度目の予告をされました。ここでは、ペトロは、イエスさまをいさめることはしていません。前回の時には、イエスさまから、「サタン、引き下がれ。あなたはわたしの邪魔をする者。神のことを思わず、人間のことを思っている」(16章23節)と言われてしまいましたから、反論することはしなかったのでしょう。それでは、ペトロと他の弟子たちは、イエスさまが言われたことを理解したのでしょうか?正しく受け止めたのでしょうか?23節には、イエスさまの言葉を聞いた弟子たちの様子が書かれています。「弟子たちは非常に悲しんだ」。
弟子たちは、イエスさまの言葉を聞いて、どうしたかというと、非常に悲しんだ、というのです。ここから分かることは、弟子たちは、イエスさまは、ご自分が殺される、と言われた。このことは、これから本当に起こることなのだろうか?と複雑な思いで聞いていたのかもしれません。私たちの愛するイエスさまが殺されることになるなんて、そんなことがあってほしくない・・・、ととても悲しい気持ちで聞いていたのかもしれません。しかし、弟子たちは、肝心なことを聴き洩らしていたようです。イエスさまは、「殺されるが、三日目に復活する」と言われましたが、復活、このことについては、何も反応がありませんでした。
いつもイエスさまと行動を共にして、その語られること、行なわれること、イエスさまの一挙手一投足を見ていたのに、聞いていたにも関わらず、弟子たちは、イエスさまが救い主としてなされることについては、まだこの時、よく分かっていなかったようです。このようなことを考えますと、私たちも、この弟子たちと同じで、イエスさまのことも、信仰のことも、まだぼんやりとしたもの、はっきりとは分かっていないことだらけではないでしょうか。そういう私たちは、イエスさまのことを共に学ぼう、神さまの言葉、神さまの示される生き方を共に学ぼう、とこの地上での生涯、天の国に帰るまで、求道者として、主の道を求め続ける者として、歩んでいくのです。
イエスさまと弟子たちの福音宣教の拠点は、ガリラヤのカファルナウムでした。そこで起こったある出来事が、24節以下に書かれています。
17:24 一行がカファルナウムに来たとき、神殿税を集める者たちがペトロのところに来て、「あなたたちの先生は神殿税を納めないのか」と言った。
弟子たちは、神殿税を徴収する人たちから、このような質問を受けます。「あなたたちの先生は神殿税を納めないのか」。神殿税については、新共同訳聖書の付録の用語解説をご覧いただきますと、このように書かれています。「出エジプト記30章11節以下に定められた規定に従って、ユダヤ人成人男子が年に一度、神殿に納める税金。額は旧約では半シェケル、新約時代には2ドラクメであった」とあります。ユダヤの人たちは、神さまの律法に従って、これを納めました。神殿税は、神殿の運営や修理など、その維持費として使用されました。
この質問に対して、ペトロはどうしたかというと、25節以下をお読みします。
17:25 ペトロは、「納めます」と言った。そして家に入ると、イエスの方から言いだされた。「シモン、あなたはどう思うか。地上の王は、税や貢ぎ物をだれから取り立てるのか。自分の子供たちからか、それともほかの人々からか。」17:26 ペトロが「ほかの人々からです」と答えると、イエスは言われた。「では、子供たちは納めなくてよいわけだ。17:27 しかし、彼らをつまずかせないようにしよう。湖に行って釣りをしなさい。最初に釣れた魚を取って口を開けると、銀貨が一枚見つかるはずだ。それを取って、わたしとあなたの分として納めなさい。」
ペトロは、神殿税を「納めます」と答えました。そして、弟子たちが住んでいた家に入ると、そこでイエスさまの方から、このようなことを言われた、ということです。「シモン、あなたはどう思うか。地上の王は、税や貢ぎ物をだれから取り立てるのか。自分の子供たちからか、それともほかの人々からか」。これに対して、ペトロは、「ほかの人々からです」と答えました。すると、イエスさまは、「では、子供たちは納めなくてよいわけだ」と言われました。神殿というのは、神さまの宮、神さまを礼拝するところです。そして、自分たちは、神さまの子供です。そうであるならば、神さまの子供は、親である神さまのための税金を払わなくてもよい、と言っているのです。税金を払わなくてもよい。何か反社会的な、非常識なことを言っているようにも聞こえますが、イエスさまが、ここで言われたことは、ただ一つのことです。それは、私たちは、神さまの子供である、ということです。
ですから、この後、イエスさまはこのようなことを言われました。「しかし、彼らをつまずかせないようにしよう。湖に行って釣りをしなさい。最初に釣れた魚を取って口を開けると、銀貨が一枚見つかるはずだ。それを取って、わたしとあなたの分として納めなさい」。イエスさまは、彼らを躓かせないようにしよう、と言われました。私たちは、神さまの子供であり、神殿税、つまり、神さまの宮のための税金を払わなくてもよい。しかし、このことは、この世においては、この社会においては理解されることではない。むしろ、この社会に生きる人たちにとっては、躓きになってしまうことになる。だから、神殿税を納めよう、と言われたのです。そして、魚を釣って、その口から出た銀貨を税金として納めなさい、と言われました。これは、例えば、一つの解釈としては、働いたお金から社会における責任を果たすように、という意味だと説明される方がありますが、「彼らをつまずかせないようにしよう」と言われたイエスさまの言葉というのは、イエスさまの弟子たちが誤解されないように、ということだけでなく、神さまの子供として、世の光、地の塩として(5章13~16節参照)、世にある人たちに、神さまの愛と義を示していく、善いことを示していく、という積極的なメッセージとして語られていたと考えてもいいのではないかと思います。
(むすび)
今日の説教題は、「神の子の自由」と付けました。今日の聖書の言葉の中に、「自由」という言葉は出ていませんが、イエスさまが言われたこの言葉、「では、子供たちは納めなくてよいわけだ」(26節)。これは、直訳的に訳すと、「それゆえ、息子たちは〔税金から〕自由なのだ」(岩波訳)となります。神さまの子供は、自由だというのです。自由というと、勝手気ままに生きるとか、好きなように生きるということを考えるかもしれません。しかし、イエスさまは、そういう意味で、自由と言われたわけではありません。私たちが、イエス・キリストを信じて知らされた、体験した自由は、罪からの自由です。そして、神さま以外の何ものにも支配されない自由です。神さまは、私たちを自由な者としてお造りになり、生かしてくださいました。残念ながら、私たち自身は、お互いを支配しようと、束縛しようとしてしまうことがあります。例えば、親は子供を自分のもの、自分の所有物のように考えてしまうことがあります。ある方は、イエスさまを信じ、聖書の言葉から学んで、そういう考え方は間違いなのだ。子供は神さまから与えられたもの、神さまのものであり、私の所有物ではない。このことに気づかされました、と素晴らしい悔い改めの言葉を証しされました。私たちは、それぞれが一人の人間、一人の人格として生きる者、自分で自由を選び取っていくのです。ただ、その自由をどのように使うか、このことが大切なことです。神さまに祈り、神さまの言葉に聴きながら、神さまから与えられた自由をどのように使うか、考えていくのです。
教会学校、祈祷会では、今、ガラテヤの信徒への手紙から学んでいますが、ガラテヤの信徒への手紙5章13節には、このような言葉が書かれています。
5:13 兄弟たち、あなたがたは、自由を得るために召し出されたのです。ただ、この自由を、肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに仕えなさい。
ここには、自由をどのように使ったらいいのかということが教えられています。「この自由を、肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに仕えなさい」とあります。愛のために、互いに仕え合うために使いなさい、と言われています。模範となるのは、イエスさまです。イエスさまがそのように生きられたのです。私たちは、イエスさまの生き方に倣って、愛のために、互いに仕え合うために、与えられた自由を使っていくのです。与えられた自由によって愛する、互いに仕え合う。これは、別の言い方をしますと、愛すること、互いに仕え合うことを自主的に、自覚的に行うということです。人に強いられて行うとか、人に強いて行わせるということではないということです。私たちの信仰の歩みというのは、人からああしなさい、こうしなさい、と言われてするものではありません。一人一人が神さまの言葉を聴き、神さまに出会い、向き合い、そこから促されて、自分で決断して行うものです。そして、それこそが、神さまの子供の自由、神さまが教えてくださる自由な生き方です。
祈り
恵み深い私たちの主なる神さま
あなたがお送りくださった救い主イエス・キリストの恵みを感謝します。イエスさまの十字架と復活を理解できないでいる弟子たちでしたが、彼らの成長を待ちながら、愛をもって忍耐をもって、主は関わられました。今、主は私たちのことも、愛をもって忍耐をもって、関わっておられることを感謝します。
主は、私たちに神さまの子供としての自由を与えてくださいました。それは罪からの自由であり、神さま以外の何ものにも支配されない自由です。しかし、その自由を間違った使い方をしてしまい、罪に陥ることがありませんように。イエスさまの歩みに倣って、与えられた自由を愛のために、互いに仕え合うために使っていくことができますように導いてください。そして、私たちの歩みを通して、主の愛と義が表されますように。
私たちの救い主イエス・キリストのみ名によってお祈りします。 アーメン








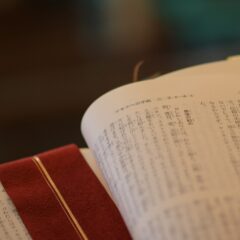

この記事へのコメントはありません。