
「主がお入り用なのです」マタイによる福音書21章1~11節 2025年11月9日
(はじめに)
イエスさまが小さなろばに乗って、エルサレムに入城された。この聖書の言葉は、受難週の時に、毎年のように読まれます。この時、イエスさまは、エルサレムの人々に歓迎されましたが、これがイエスさまの受難の始まりでした。ここから、イエスさまは、十字架と復活の道へ向かって行くことになります。
(聖書から)
イエスさまと弟子たちの一行は、エルサレムに近づいて来た時、ベトファゲというところで、二人の弟子を使いに出します。この弟子たちに主はこのように言われました。
「向こうの村へ行きなさい。するとすぐ、ろばがつないであり、一緒に子ろばのいるのが見つかる。それをほどいて、わたしのところに引いて来なさい。もし、だれかが何か言ったら、『主がお入り用なのです』と言いなさい。すぐ渡してくれる。」(2、3節)
イエスさまは、二人の弟子に、自分のために子ろばを連れて来るようにと言われました。ところで、「二人の弟子」というのは、イエスさまの弟子の中の誰のことでしょうか?この聖書個所は、マルコによる福音書、ルカによる福音書、ヨハネによる福音書にもあります。新共同訳聖書では、「エルサレムに迎えられる」という小見出しの次の行に、それぞれの福音書の聖書個所が書かれています。引照付きの聖書をお持ちの方は、引照を使って開いてみてもよいでしょう。他の福音書を見てみると、マルコによる福音書とルカによる福音書には、この福音書と同じように、「二人の弟子」とありました。つまり、二人の弟子の名前は書かれていないのです。私は、このマタイによる福音書を読み進めてきて、少し前の聖書個所に出てきたイエスさまの二人の弟子のことが気になりました。
20章20~28節には、「ヤコブとヨハネの母の願い」という小見出しが付けられた聖書個所があります。イエスさまの弟子のヤコブとヨハネ、彼らはゼベダイの息子で兄弟でした。この弟子たちが、イエスさまから弟子としての招きを受ける場面が聖書に書かれています(4章21、22節)。
「そこから進んで、別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、父親のゼベダイと一緒に、舟の中で網の手入れをしているのを御覧になると、彼らをお呼びになった。この二人もすぐに、舟と父親とを残してイエスに従った」。
イエスさまは、ガリラヤ湖のほとりを歩いていた時、漁をしていた漁師のシモン(ペトロ)とアンデレという二人の兄弟をご自分の弟子になるようにお招きになり、「わたしについて来なさい。人間をとる漁師にしよう」(4章19節)と言われました。彼らは主の招きに応えて、弟子になりました。それに続いて、主はゼベダイの息子ヤコブとその兄弟ヨハネをお招きになりました。この聖書個所には書いてありませんが、おそらく、彼らに対しても主は同じように、「わたしについて来なさい。人間をとる漁師にしよう」と言われたと思います。ヤコブとヨハネもイエスさまの招きに応えていきました。
そういう二人ですが、20章では、彼らの母がイエスさまにお願いに来たのです。それが、「王座にお着きになるとき、この二人の息子が、一人はあなたの右に、もう一人は左に座れるとおっしゃってください」(20章21節)ということでした。ちなみにマルコによる福音書では、母ではなくて、彼ら自身の願いとして、このことが書かれています(マルコ10章35~45節参照)。そうしますと、これは母親だけの願いというだけでなく、ヤコブとヨハネの願いでもあった。つまり、家族みんなの願いであったと考えられます。
これに対して、イエスさまは、「あなたがたの中で偉くなりたい者は、皆に仕える者になり、いちばん上になりたい者は、皆の僕になりなさい。人の子が、仕えられるためではなく仕えるために、また、多くの人の身代金として自分の命を献げるために来たのと同じように」(20章26~28節)と言われました。ゼベダイの息子たちの母、そして、彼ら自身の願いは、偉くなりたい、上に立つ者になりたい、ということだったようですが、主は、仕える者になりなさい、僕となりなさい、と言われました。それはイエスさまご自身が仕える者として、僕としておいでになったからでした。
私は、イエスさまとこの弟子たちの会話を読んで、自分が仕える者として生きるとか、僕として生きるということは、いつも意識していなければならないこと、気をつけていなければならないことだと思いました。と言うのは、私たちは、このことを意識していないと、気をつけていないと、すぐにその反対の道を進んでしまうのです。熱心に聖書を学んでも、活動をしても、自分が仕える者であること、僕であることを忘れるならば、何のために聖書を読むのか、活動をするのか、別な目的になってしまい、イエスさまの歩みとは遠く離れたものになってしまうのです。
そういうことで、イエスさまとヤコブとヨハネの間でのやり取りを考えますと、もしかすると、イエスさまが子ろばを連れて来るように、と遣わした二人の弟子というのは、ヤコブとヨハネだったかもしれません。このことを通して、主は彼らに大切なことを教えようとされたのかもしれません。
ところで、遣わされた弟子たちは、イエスさまがなぜ、子ろばを連れて来るように言われたのだろう?と不思議に思ったかもしれません。この子ろばについて、マタイによる福音書には書かれていませんが、マルコによる福音書、ルカによる福音書には、「まだだれも乗ったことのない子ろば」(マルコ11章2節、ルカ19章30節)と書いてあります。まだ人を乗せたことのない未経験な、未熟なろばです。それが何の役に立つのでしょうか。
一方、このマタイによる福音書では、先ほどお読みしたように、「向こうの村へ行きなさい。するとすぐ、ろばがつないであり、一緒に子ろばのいるのが見つかる」とあります。後で読む7節にも「ろばと子ろばを引いて来て」とあります。子ろばだけでなく、もう一頭のろばも連れて来たことになります。
これらのろばは何のために使われるのかというと、「もし、だれかが何か言ったら、『主がお入り用なのです』と言いなさい。すぐ渡してくれる」とありますように、「主がお入り用なのです」、主が用いられるためなのです。
人を乗せたことのない子ろば。しかし、主は、その子ろばをご自分のために用いようとされました。なぜ、わざわざ子ろばを用いようとされたのでしょうか?それは、聖書の言葉が実現するためでした。
21:4 それは、預言者を通して言われていたことが実現するためであった。
21:5 「シオンの娘に告げよ。『見よ、お前の王がお前のところにおいでになる、/柔和な方で、ろばに乗り、/荷を負うろばの子、子ろばに乗って。』」
ここには、イザヤ書62章11節とゼカリヤ書9章9節の言葉が引用されています。ここに書かれていることは、王がおいでになること、その方は柔和な方でろばの子に乗ってやって来る、ということです。最新の聖書協会共同訳では、このように訳されています。「見よ、あなたの王があなたのところに来る。/へりくだって、ろばに乗り、/荷を負うろばの子、子ろばに乗って」。「柔和な方」というところが、「へりくだって」となっています。主は、へりくだった方としておいでになったのです。これは、ヤコブとヨハネ、そして、弟子たちとの会話の中で主が語られたこと、仕える者、僕ということと通じます。
二人の弟子は、主が言われたことに対して、どうしたでしょうか。
21:6 弟子たちは行って、イエスが命じられたとおりにし、21:7 ろばと子ろばを引いて来て、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。
「行って、イエスが命じられたとおりにし」とあります。主の弟子は、主が命じられたとおりにするのです、主が言われたことに従うのです。なぜなら、そのことによって聖書の言葉は実現するからです。神さまのみ心が行われるからです。
(むすび)
子ろば、それは、主の弟子たちのことを示しているようです。まだ人を乗せたことのない未経験な子ろば、それが十分にイエスさまをお乗せするようなことができるのでしょうか?マタイによる福音書では、もう一頭のろばのことが書いてありました。もしかすると、そのろばというのは、子ろばを助ける、支える役割のためだったかもしれません。私たちは、子ろばのような者であり、また子ろばを助け、支えるろばのような者ではないでしょうか。
21:8 大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また、ほかの人々は木の枝を切って道に敷いた。21:9 そして群衆は、イエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。
「ダビデの子にホサナ。主の名によって来られる方に、祝福があるように。いと高きところにホサナ。」
「ホサナ」とは、「私たちを救ってください」という意味です。エルサレムの大勢の群衆はイエスさまがおいでになったことを歓迎しました。
21:10 イエスがエルサレムに入られると、都中の者が、「いったい、これはどういう人だ」と言って騒いだ。21:11 そこで群衆は、「この方は、ガリラヤのナザレから出た預言者イエスだ」と言った。
この方は、預言者だとも言っています。このように大歓迎されたイエスさまでしたが、この「ホサナ」の賛美が、後には、別の言葉に変わっていくことになります(27章15~26節参照)。
主は、ろばの子に乗っておいでになりました。主が用いられた子ろばとは、小さなものであり、まだ人を乗せたこともなかった未熟なものでした。しかし、主はその子ろばを用いられました。私たちは、この子ろばのような者ですが、「主がお入り用なのです」とあるように、主は、そういう私たちを用いてくださいます。主は、小さな者、弱い者を用いてくださいます。
主は、柔和な方、へりくだった方、仕える者、僕として、私たちのところにおいでになりました。ろばの子というのは、平和の象徴と言われます。そのろばの子に乗っておいでになった主は平和の王です。平和は、どのようにしたら実現するのでしょうか?私は、平和は、イエスさまの歩み、イエスさまの生き方に倣っていくことによって実現していくと信じています。私たちは、お互いに仕え合う、お互いが僕として生きるのです。私たちの生きるこの国が、私たちの生きるこの世界が平和になるために、主の歩み、主の生き方に倣っていきましょう。最後に山上の説教で語られたイエスさまの言葉を聖書協会共同訳の訳でお読みして終わります。
「へりくだった人々は、幸いである/その人たちは地を受け継ぐ。」(マタイ5章5節)
祈り
恵み深い私たちの主なる神さま
主は、小さなろばの子に乗って、エルサレムに入城されました。それは聖書の言葉が実現するためでした。主は王として歓迎されました。しかし、主はこの世の王とは違い、柔和な方、へりくだった方としておいでになりました。仕える者、僕として歩まれました。私たちも聖書が示す本当の平和を願って生きる者にしてください。平和を祈りつつ、主に倣って生きる者、仕える者、僕として生きる者にしてください。
私たちの救い主イエス・キリストのみ名によってお祈りします。 アーメン


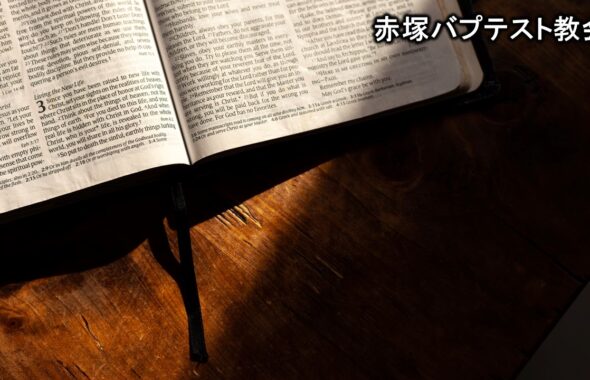





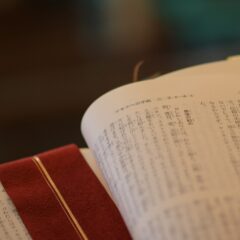

この記事へのコメントはありません。