
成し遂げられた ヨハネによる福音書19章16b~30節 2025年 4月13日
聖書―ヨハネによる福音書19章16b~30節
(はじめに)
今日から受難週です。この受難週の後に、来週の日曜日に復活祭、イースターを迎えます。キリスト教会のお祝いというと、クリスマスが知られていますが、実は、イースターこそは、最も大切なお祝いです。歴史的には、クリスマスは、紀元四世紀の中ごろからお祝いされるようになったということですが、イースターは、それよりも前の紀元一世紀中ごろからお祝いされていたそうです。クリスマスというのは、皆さんよくご存じのように、神さまが私たちのためにご自分のみ子であるイエス・キリストをこの世にお送りくださった出来事をお祝いするものです。イースターは、イエス・キリストが、私たちを罪から救うために、十字架にかかってご自分の命をおささげになり、死なれ、葬られましたが、その三日目に復活されたことをお祝いするものです。この一週間、イエスさまの十字架の出来事を思いめぐらして過ごしてまいりましょう。
(聖書から)
お読みした聖書個所は、ヨハネによる福音書19章16節の後半からです。イエスさまは、いよいよゴルゴタの丘で、十字架につけられます。17節には、このようなことが書かれています。
19:17 イエスは、自ら十字架を背負い、いわゆる「されこうべの場所」、すなわちヘブライ語でゴルゴタという所へ向かわれた。
今朝、教会学校に出席された方は、お気づきになられたと思いますが、イエスさまが刑場であるゴルゴタの丘へ向かう時、イエスさまのおつきになる十字架を担いだ人のことが、マタイによる福音書には書かれていました。キレネ人シモン、この人は、ローマの兵士たちによって無理やり、イエスさまの十字架を担がされたのです(マタイ27章32節)。
ヨハネによる福音書の著者であるヨハネは、そのことを書きもらしてしまったのでしょうか?いいえ、そうではありません。ヨハネがここで伝えたかったこと、それは、イエスさまがご自分で決断して十字架を背負われた、十字架につけられた、ということです。それでヨハネは、「イエスは、自ら十字架を背負い」と書いたのです。続いて18節以下をお読みします。
19:18 そこで、彼らはイエスを十字架につけた。また、イエスと一緒にほかの二人をも、イエスを真ん中にして両側に、十字架につけた。19:19 ピラトは罪状書きを書いて、十字架の上に掛けた。それには、「ナザレのイエス、ユダヤ人の王」と書いてあった。19:20 イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がその罪状書きを読んだ。それは、ヘブライ語、ラテン語、ギリシア語で書かれていた。
イエスさまを真ん中にして、両脇に他の二人の犯罪人がそれぞれ十字架につけられました。総督ピラトが罪状書きを書いて、イエスさまの十字架に掛けました。その罪状書きには、「ナザレのイエス、ユダヤ人の王」と書いてあったということです。マタイによる福音書では、「これはユダヤ人の王イエスである」(マタイ27章37節)とありました。ヨハネによる福音書の方が、少し詳しく書いてあることが分かります。しかも、20節にあるように、「イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がその罪状書きを読んだ。それは、ヘブライ語、ラテン語、ギリシア語で書かれていた」ということも書かれています。罪状書きが、ヘブライ語、ラテン語、ギリシア語で書かれていた、というのはどういうことかというと、当時の地中海沿岸の国々の言葉で書かれていた、ということです。ヘブライ語というのは、ユダヤ人の言葉です。ラテン語というのは、総督ピラトなど、ローマ人の言葉です。そして、ギリシア語は、広く地中海地域で公用語として使われていた言葉です。このことから分かることは、この罪状書きを書いたピラトという人は、イエスさまという方を、誰にでも分かるように表した、ということです。
ところが、これに対して、ユダヤ人の祭司長たちがクレームをつけます。そのやり取りを読んでみます。
19:21 ユダヤ人の祭司長たちがピラトに、「『ユダヤ人の王』と書かず、『この男は「ユダヤ人の王」と自称した』と書いてください」と言った。19:22 しかし、ピラトは、「わたしが書いたものは、書いたままにしておけ」と答えた。
「ユダヤ人の王」と書いたことに対して、「この男は『ユダヤ人の王』と自称した」と書き直すように要求しています。ピラトはどうしたかというと、「わたしが書いたものは、書いたままにしておけ」と答えています。書き直すことはしなかったのです。先週お話ししたように、ピラトは、イエスさまを尋問しましたが、何の罪も見当たりませんでした。しかし、ユダヤ人たちに押されて、ついにイエスさまを十字架につけることになりました。けれども、ピラトの心の中は、何か複雑なものがあったように思います。イエスさまという方は真実な方、罪のない方・・・。ピラトは、そのことをイエスさまとの会話を通して気づかされていったのではないでしょうか。そのことが、このやり取りには表されているのではないでしょうか。
23、24節には、ローマの兵士たちが、イエスさまの衣服を、誰のものになるか、くじ引きで決めようとしている様子が書かれていて、そのことについて、詩編22編19節が引用され、イエスさまの十字架の出来事が、聖書の実現であったことを示しています。
そして、その後には、イエスさまの十字架のそばにいた人たちのことが書かれています。
19:25 イエスの十字架のそばには、その母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。19:26 イエスは、母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、母に、「婦人よ、御覧なさい。あなたの子です」と言われた。19:27 それから弟子に言われた。「見なさい。あなたの母です。」そのときから、この弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。
イエスさまの十字架のそばにいた人について、「その母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリア」とあります。「その母」というのは、イエスさまの母マリアのことです。そして、その姉妹、クロパの妻マリア、マグダラのマリアといった人たちがいたということです。これらを見てみると、マタイによる福音書とは、内容が一致していないように思えますが、マタイでは、「大勢の婦人たちが遠くから見守っていた。この婦人たちは、ガリラヤからイエスに従って来て世話をしていた人々である。その中には・・・」(マタイ27)55、56節)とあるように、イエスさまの十字架を見守っていた人たちというのは、ここに名前が出てくる人たちだけではなかった、ということのようです。
ところで、その中には、「母とそのそばにいる愛する弟子」とありますように、母、これは、イエスさまの母のことですが、そのそばに愛する弟子がいた、ということです。ここに書かれている愛する弟子とは、誰のことでしょうか?ヨハネによる福音書には、この愛する弟子ということが何度か出てきます。「弟子たちの一人で、イエスの愛しておられた者」(13章23節)、「イエスが愛しておられたもう一人の弟子」(20章2節)、「イエスの愛しておられたあの弟子」(21章7節)、「イエスの愛しておられた弟子」(21章20節)。
さて、繰り返しますが、この愛する弟子とは、誰のことでしょうか?ある説では、ヨハネによる福音書だけにしか、この愛する弟子という言葉が出て来ないことから、ヨハネによる福音書を書いたヨハネ自身のことではないか?イエスさまの十二弟子の一人のヨハネのことではないか?と言われます。しかし、このヨハネによる福音書のすべてを読んでも、その名前は明らかになっていませんので、はっきりとは分かりません。
イエスさまは、ご自分の母と愛する弟子に、それぞれこのようなことを言われました。母には、「婦人よ、御覧なさい。あなたの子です」と言われ、愛する弟子には、「見なさい。あなたの母です」と言われました。イエスさまは、ご自分が十字架につけられ、死を迎える直前に、彼らにこのようなことを言われたのです。
ところで、イエスさまの母マリア、そして、イエスさまの弟子の一人でおそらくはヨハネだと思われますが、ここには、どちらの名前も出てきません。イエスさまの母とイエスさまの愛する弟子。そのようにしか書かれていないというのは、不思議な気がします。このことについて、ある方は、次のような説明をしています。それは、イエスさまの母というのは、教会を指している。イエスさまの愛する弟子というのは、イエスさまを信じる私たちを指しているというのです。そこでここでは、あえて、その名前を呼ばなかったのだ、というのです。「そのときから、この弟子はイエスの母を自分の家に引き取った」とありました。イエスさまの愛する弟子、つまり、私たちに、母、つまり、教会が与えられた。主は、そのようにして、主を信じる私たちが教会に生きる者としてくださった、というのです。
主は、神さまの選びによって母となられたマリアを、十字架の死を前に、ご自分の愛する弟子に託されました。それは、十字架の下(もと)で、新しい家族が生まれたということです。私たちは主によって、神の家族とされたのです。
(むすび)
19:28 この後、イエスは、すべてのことが今や成し遂げられたのを知り、「渇く」と言われた。こうして、聖書の言葉が実現した。19:29 そこには、酸いぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々は、このぶどう酒をいっぱい含ませた海綿をヒソプに付け、イエスの口もとに差し出した。19:30 イエスは、このぶどう酒を受けると、「成し遂げられた」と言い、頭を垂れて息を引き取られた。
イエスさまの最期の様子を読みました。イエスさまは、「渇く」と言われ、最期に「成し遂げられた」と言われて息を引き取られた、ということです。「成し遂げられた」とありました。日本語訳の聖書では、この言葉はいろいろな言葉で訳されています。「すべてが終った」(口語訳)、「完了した」(新改訳)。これらの言葉が意味していることは、神さまの救いのご計画のことです。神さまの救いが成し遂げられた、ということが言われているのです。
私たちは、自分が救われるために、何をしなければならないでしょうか?一生懸命、善行を積んだり、修行をしたりすることでしょうか?いいえ、私たちは、自分で自分を救うことはできないのです。私たちが救われるためにするべきこと、それはただ一つです。それはイエスさまを心にお迎えして、その救いを受け取ることです。
ところで、聖書が示す救いというのは、罪からの救いです。私たち人間は、自分で罪を克服することはできない、罪から離れることはできないのです。パウロは、自分自身のことをこう言っています。「わたしは自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている」(ローマ7章19節)。善というのは、神さまに従って生きる心のことです。私は神さまに従っていこう、人を愛する生き方に努めよう、と願っているけれども、それとは反対に、神さまに従わない心、人を愛さない、憎む心がある。自分の心には、罪があるのだ、と言っているのです。これは、私たちも同じではないでしょうか。信仰生活を何年歩んできても、どんなに伝道をしても、奉仕をしても、献金をしても、聖書を深く学んでも、長い時間お祈りしても、罪は自分で解決することはできない、克服することはできないのです。しかし、そういう私たちを神さまは新しく生きることができるように、神さまの愛に生きることができるように、私たちのために、救い主をお送りくださったのです。救いを成し遂げてくださったイエス・キリストを自分の人生に、心にお迎えして歩んでまいりましょう。
祈り
恵み深い私たちの主なる神さま
神さまのみ子イエス・キリストを私たちにお送りくださり、与えてくださったことを感謝します。
私たちは、自分の力や知恵では、神さまに従うことも、人を愛することもできません。私たちの心の中は、すぐに揺れ動き、善いことを求めても、悪いことを考えたりしてしまう、一人の罪人です。しかし、そういう私たちのために、イエスさまがおいでくださって、私たちを罪から救うために十字架につけられました。イエスさまは、十字架につけられ、最期を迎えられる時、「成し遂げられた」と言われました。私たちのために、ご自分の命をささげられ、救いを成し遂げられました。
次週は、イエスさまの復活をお祝いする礼拝です。イエスさまは、十字架につけられ、死なれましたが、三日目に復活されました。そのイエスさまを、自分の人生にお迎えしていく時に、主は、私たちを新しく生きることができるように、愛の人として歩むことができるようにしてくださいます。どうぞ、私たちを導いてください。
私たちの救い主イエス・キリストのみ名によってお祈りします。 アーメン








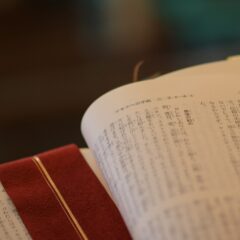

この記事へのコメントはありません。