
「この最後の者にも」マタイによる福音書20章1~16節 2025年10月5日
聖書―マタイによる福音書20章1~16節
(はじめに)
「天の国は次のようにたとえられる」(1節)。イエスさまのたとえ話は、このような言葉から始まります。「天の国は・・・」という言葉が示しているように、イエスさまのたとえ話は、天の国についてのお話しです。つまり、イエスさまは私たちに、天の国の住人はどのように生きていくのか、ということを教えられたのです。
(聖書から)
今日は、マタイによる福音書20章1~16節をお読みしました。この聖書個所について、新共同訳聖書では、「『ぶどう園の労働者』のたとえ」という小見出しが付けられています。1、2節をお読みします。
20:1 「天の国は次のようにたとえられる。ある家の主人が、ぶどう園で働く労働者を雇うために、夜明けに出かけて行った。20:2 主人は、一日につき一デナリオンの約束で、労働者をぶどう園に送った。
「ある家の主人」というのは、ぶどう園の持ち主のことでしょう。主人はぶどう園で働く労働者を雇うために、夜明けに出かけて行った、ということです。彼らを一日につき一デナリオンという金額で雇っていたということです。新共同訳聖書をお持ちの方は、聖書の後ろの方に「度量衡および通貨」という付録が付いていますので、そこをご覧ください。デナリオンについて、「ローマの銀貨で、1デナリオンは、1ドラクメと等価(1日の賃金に当たる。)」と説明があります。一デナリオンというのは、一日の労働賃金だったということです。
3節以下をお読みします。
20:3 また、九時ごろ行ってみると、何もしないで広場に立っている人々がいたので、20:4 『あなたたちもぶどう園に行きなさい。ふさわしい賃金を払ってやろう』と言った。20:5 それで、その人たちは出かけて行った。主人は、十二時ごろと三時ごろにまた出て行き、同じようにした。
九時頃というのは、朝の九時頃のことです。何もしないで広場に立っている人々がいた、ということです。ここには、「何もしないで」と書いてありますので、ただブラブラしていた人というふうに思われるかもしれませんが、おそらく、仕事がなくてどうしようか、と困っていた人々ではないかと思います。そういう人たちを見つけて、ぶどう園の主人はこう言います。「あなたたちもぶどう園に行きなさい。ふさわしい賃金を払ってやろう」。「ふさわしい賃金」というのは、生きていくために必要な分ということでしょう。それが一デナリオンであったということです。この後、主人は、十二時頃、これは正午頃のこと、三時頃、これは午後三時頃ということでしょう。何度も出て行き、広場にいる人たちに声をかけて、ぶどう園で働くように導いた、ということです。
続いて、6節以下をお読みします。
20:6 五時ごろにも行ってみると、ほかの人々が立っていたので、『なぜ、何もしないで一日中ここに立っているのか』と尋ねると、20:7 彼らは、『だれも雇ってくれないのです』と言った。主人は彼らに、『あなたたちもぶどう園に行きなさい』と言った。
今度は、午後五時頃の話です。主人が広場に行ってみると、そこには人々が立っていました。主人は「なぜ、何もしないで一日中ここに立っているのか」と尋ねると、彼らはこう答えました。「だれも雇ってくれないのです」。午後五時頃の話です。もう暗くなってきて、仕事もできなくなる時間帯です。彼らは決してブラブラあてもなく過ごしてきたわけではありません。なぜなら、彼らは「だれも雇ってくれないのです」と答えているからです。ずっと仕事を捜してこの時間まで立っていた、待っていたのです。主人は彼らにこう言いました。「あなたたちもぶどう園に行きなさい」。
夕方になって、仕事時間も終わり、主人は賃金払いをすることになりました。その時のことが、8節以下に書かれています。
20:8 夕方になって、ぶどう園の主人は監督に、『労働者たちを呼んで、最後に来た者から始めて、最初に来た者まで順に賃金を払ってやりなさい』と言った。20:9 そこで、五時ごろに雇われた人たちが来て、一デナリオンずつ受け取った。20:10 最初に雇われた人たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし、彼らも一デナリオンずつであった。
このたとえ話では、朝の九時頃に雇われた人たち、正午頃に雇われた人たち、午後三時頃に雇われた人たち、そして、午後五時頃に雇われた人たちがいたということです。すると、働いた時間はそれぞれ違います。しかし、どの人たちも一デナリオンずつ受け取った、ということです。興味深いことに、10節には、「最初に雇われた人たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし、彼らも一デナリオンずつであった」と書いてあることです。最初に雇われた人たちというのは、朝の九時頃に雇われた人たちのことでしょう。彼らは、その後に雇われた人たちよりも長い時間、働いた人たちです。彼らはこう考えたのです。「私たちは長い時間、汗水流して働いた。後から雇われた人たちよりも多く賃金をもらえるのは当然だろう!」ところが、そうではなかったのです。朝九時頃からの人も、一番後に雇われた人も、みんな同じ一デナリオンの賃金を受け取ったというのです。
このたとえ話について、おかしな話だなあ、と思う方がおられるかもしれません。ある牧師先生が、この聖書個所から説教しました。その時の説教題というのが、「おかしな賃金払い」という題でした。確かにおかしな話です。
11節以下をお読みします。
20:11 それで、受け取ると、主人に不平を言った。20:12 『最後に来たこの連中は、一時間しか働きませんでした。まる一日、暑い中を辛抱して働いたわたしたちと、この連中とを同じ扱いにするとは。』 20:13 主人はその一人に答えた。『友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたはわたしと一デナリオンの約束をしたではないか。20:14 自分の分を受け取って帰りなさい。わたしはこの最後の者にも、あなたと同じように支払ってやりたいのだ。20:15 自分のものを自分のしたいようにしては、いけないか。それとも、わたしの気前のよさをねたむのか。』 20:16 このように、後にいる者が先になり、先にいる者が後になる。」
最初に雇われた人たちは、主人に抗議します。「最後に来たこの連中は、一時間しか働きませんでした。まる一日、暑い中を辛抱して働いたわたしたちと、この連中とを同じ扱いにするとは」。すると、主人はこう答えました。「友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたはわたしと一デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。わたしはこの最後の者にも、あなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしては、いけないか。それとも、わたしの気前のよさをねたむのか」。
ここで主人が、自分に抗議した人に対して、「友よ」と呼んでいることは印象的です。決して、対立するような思いではないことが分かります。主人は、彼らに対して、私の言うことを分かってほしい。私の思いを、気持ちを受け止めてほしい、と心から願って語ったのでしょう。
主人の答えは、不当なことはしていない、ということでした。なぜなら、2節にありますように、主人は自分が雇う人すべてに、一日一デナリオンの賃金を払うと約束していたからです。決して、不当な、不正なことはしていなかったのです。そればかりか、次の言葉には、主人の思い、気持ちが表れています。「わたしはこの最後の者にも、あなたと同じように支払ってやりたいのだ」。
「この最後の者」というのは、午後五時頃に雇われた、最後に雇われた人たちのことでしょう。一日一デナリオンというのは、人が一日を生きていくために必要な金額でした。わずかな時間しか働かなかったから、あなたには一デナリオンは払えません。主人はそう考えませんでした。自分が雇うすべての人がその日その日を生きていくことができるように、と一デナリオンずつ支払ったのです。
ところで、このたとえ話というのは、世の中で、会社などでそのまま適応できるかというと、そういうことではないでしょう。最初に言いましたように、このたとえ話は、天の国のたとえ話です。神さまを信じるとはどういうことか、神さまを信じる人の生き方を教えているのです。ぶどう園の主人というのは、ここまでお話ししてきてお分かりになったと思いますが、神さまのことです。そして、ぶどう園で働くように雇われた人たちというのは、私たち一人一人のことです。
一日一デナリオンの賃金ということ、これは、私たちが一日一日生きていくために必要なもの、神さまの恵みということです。ところが、最初に雇われた人というのは、神さまの恵みを恵みとしてではなく、報酬と考えたのです。報酬とは、自分の働きに見合った分で得ることのできる収入ということです。世の中の、仕事の場合は、そういう考えです。しかし、天の国の考え、神さまの恵みということで言うなら、私たちは、自分はこれだけ働いたから、伝道した分、奉仕した分、献金した分、その働き、行いに応じて、天国に行けるとか、天国の特等席に行けるということではないのです。ぶどう園の主人がどの時間から働いた労働者に対しても、一日一デナリオンずつ与えたように、神さまは、私たち一人一人に対して、生きるために必要なものをそれぞれ等しく与えてくださるお方。そのことがこのたとえ話が語っていることではないでしょうか。
(むすび)
今日のイエスさまのたとえ話にこのような言葉がありました。「自分のものを自分のしたいようにしては、いけないか。それとも、わたしの気前のよさをねたむのか」(15節)。この言葉にあるように、神さまという方は、気前の良いお方です。ここに出てくる「気前の良い」という言葉は、「善い」という意味です。神さまは善いお方です。神さまのなさることは善いことなのです。私たちは、神さまのなさる善いことをアーメンと言って、受け入れていくのです。
一方、私たち人間はどうでしょうか?ここには、「妬み」ということが言われていましたが、すぐに妬んでしまう。人と自分を比べて妬んでしまう。ある方はこう言いました。「自分が試練に遭った時は同情してくれる人はいるけれど、嬉しいことがあった時に一緒に喜んでくれる人はあまりいない」。他人の喜びを喜びとできないというのです。ローマの信徒への手紙12章15節に「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい」という言葉がありますが、ある方は「泣く人と共に泣くことよりも、喜ぶ人と共に喜ぶ、このことの方が難しい」と言いました。そして、「他人の喜びを喜びとできないでいる、そういう自分自身に問題を感じる」とも言われました。私は、その方が、真摯な態度で神さまの前に立ち、神さまの光に自分を照らしておられる姿に大変敬服しました。ところで、この聖書の言葉に出てくる「妬む」という言葉は、直訳的には「目が悪くなっている」(マタイ6章23節参照)という意味です。心の目が悪くなっている、見えなくなっている。それは神さまの恵みを見失っているということです。その時、私たちは、自分が神さまの恵みをいただいていることを忘れていますから、分からなくなっていますから、他人を妬んでしまうのです。
神さまの恵みを恵みとして受け取っていく。このことも難しいことだと思います。私たちは、神さまの恵みを恵みとして受け取ることをしないで、すべては自分の力で得たもの、報酬と考えてしまうようなことはないでしょうか。「後にいる者が先になり、先にいる者が後になる」(16節)とありました。主が言われた「後にいる者」とは、「この最後の者」(14節)のことです。ところが、自分の力で生きていると思う時、自分が「後にいる者」、「この最後の者」であることを忘れてしまうのです。神さまの恵みを、恵みとして受け取っていく時、そこには、神さまに対する感謝、喜びがあります。しかし、神さまの恵みを、報酬と考えると、そこには、誇りとか妬みが起こってきます。自分が神さまの恵みによって生かされていることをおぼえるところから、「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい」(一テサロニケ5章16~18節)。このみ言葉が私たちの中で実現していくのです。私は「この最後の者」、「後にいる者」、ただただ神さまの恵みによって愛され、生かされている者、そのことをおぼえて歩んでまいりましょう。
祈り
恵み深い私たちの主なる神さま
神さまは、ぶどう園の主人のように、雇った人たちすべてに生きるために必要なものを与えてくださるお方です。わたしたちの心の目が曇ってしまい、神さまの恵みを見失う時、私たちは喜びや悲しみを分かち合うことができなくなります。先にぶどう園に雇われた人たちが「まる一日、暑い中を辛抱して働いた」(12節)と言ったように、神さまの恵みに生きることも喜べなくなります。そういう私たちの心の目を開いてください。神さまの恵みを見つめて生きる者としてください。神さまの恵みを喜び、感謝し、互いのことを、互いの存在を喜ぶ者としてください。
私たちの救い主イエス・キリストのみ名によってお祈りします。 アーメン








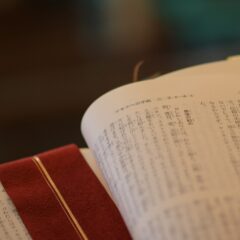

この記事へのコメントはありません。